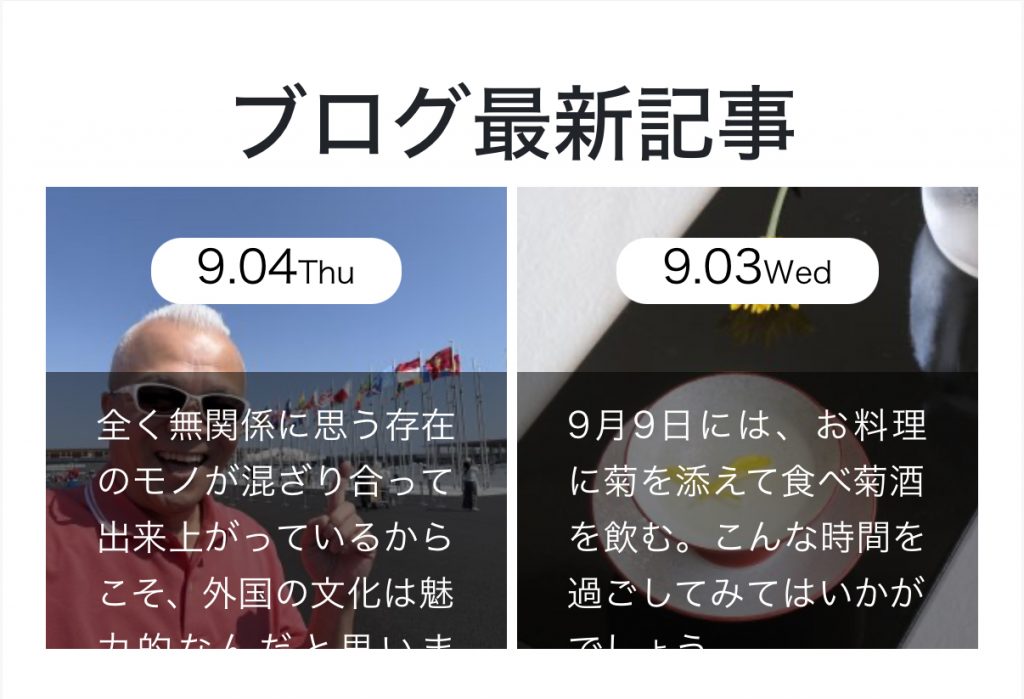「重陽」という考え方から見える、寄付をすると言う行為の本質について
ごきげんよう、こんにちは、こんばんは、内藤正風です。
一昨日の私のブログで、「重陽の節句」の事について書いたのですが、そのブログを読み返しながら思ったのです。「重陽の節句と寄付をする事って似ている」と。なので今日のブログは、そんな事について書きたいと思います。
最高は最低への入り口
東洋思想では、数には陰の数と陽の数があって、陰の数は偶数、陽の数は奇数と言われています。そして数字が0から9まである中で、陽の数の1番大きな数字「9」が重なる9月9日は"陽が極まる日"として、そのまま放っておくと悪いことが起こってしまう可能性があるので、そうならない様にしようという考え方から生まれているのが「重陽の節句」になります。
一見すると、「陽」に満たされているんだから最高の状態で良い事だと思いがちですが、そうではなく、最高は最低に向かう始まりであるというのが深いなぁと私は感じています。
つまり日本のことわざにある「過ぎたるは及ばざるがごとし」という事と、「流水は腐らず」の二つなどは、正にこの考え方の象徴的なものに外ならないからです。
独り占めしてはいけないという事
まず「過ぎたるは及ばざるがごとし」とは、何事も程度を超えてしまうと不足しているのと同じでよくない事であるという意味のことわざです。
人が独り占めしたくなるもののツートップは、運気とお金だと思うのです。運がよくなってツキが回ってきたらそのツキを何としても手放したくなくなったり、お金が入ってくるようになってくるとそのお金を手放したくなくなったりしますよね。ところがツキを独り占めしようとしたりお金を独り占めしようとした瞬間に、ツキやお金って、するっと逃げて行ってしまったりします。
正しく「過ぎたるは及ばざるがごとし」であり、独り占めしようとした瞬間から「思考も行動もおかしくなっているよ」っていう教えに他ならないと思います。
流れを止めてはいけないという事
次に「流水は腐らず」とは、水は動いていれば腐ることはないが、留まった瞬間から傷み始めるという意味のことわざになります。
先ほど書いた、独り占めするという行為は流れを止めるという事に外なりません。運気が良くなってきたら、そのツキを自分だけのものにしようとして運気の流れを止めるから、運気が悪くなってしまうのですし、お金も自分のところに入ってくるようになってきたら、そのお金を独り占めしようとするから巡りを止めてしまうようになってしまうのです。
これって呼吸を考えればわかりやすいと思います。息を吸おうと思ったら吐かなければ吸う事はできません。なのに沢山息を吸いたいからって、吸って、吸って、吸ってとしていると、そのうち息を吸えなくなって息苦しくなってしまうのです。
呼吸は吸ったり吐いたりしているから、次の新しい空気の流れが出来るのです。流水も下流に流すからこそ上流から新しい水が流れてくるのです。
つまり流れを止めるという事は、自殺行為に他ならないという教えなのです。
寄付は、独り占めをせず、流れを止めないように、自ら進んで行う行為だと思います
この「陽が極まってしまう」という考え方は、独り占めすることや流れを止める事によって起きてしまう現象だという事を、古来より世界中の人たちがその経験則として学んでおり、そうならない様にしてきているという事なのです。つまり古来より行われている「寄付」という行為です。
寄付するって、お金持ちが行なう事って思われがちですよね。しかしこれはお金が余っているからと言う考え方ではなく、陽が極まるっていうのと同じで、富を独り占めすることによって「陽が極まる」状態にしてしまっては自分に良くないことが起こってしまったり、将来がなくなってしまうと思って、意識して寄付をするようになったのだと私はそんな風に思うのです。
重陽って意味深長だなぁと改めて感じます。
内藤正風PROFILE

-
平成5年(1993年)、光風流二世家元を継承。
お花を生けるという事は、幸せを生み出すという事。あなたの生活に幸せな物語を生み出すお手伝いをする、これが「いけばな」です。
光風流の伝承を大切にしながら日々移り変わる環境や価値観に合わせ、生活の中のチョットした空間に手軽に飾る事が出来る「小品花」や、「いけばな」を誰でもが気軽に楽しむ事が出来る機会として、最近ではFacebookにおいて「トイレのお花仲間」というアルバムを立ち上げ、情報発信をしています。ここには未経験の皆さんを中心に多くの方が参加され、それぞれ思い思いに一輪一枝を挿し気軽にお花を楽しまれて大きな盛り上がりをみせており、多くの方から注目を浴びています。
いけばな指導や展覧会の開催だけにとどまらず、結婚式やパーティー会場のお花、コンサートなどの舞台装飾、他分野とのコラボレーション、外国の方へのいけばなの普及、講演など、多方面にわたり活動し多くの人に喜ばれています。