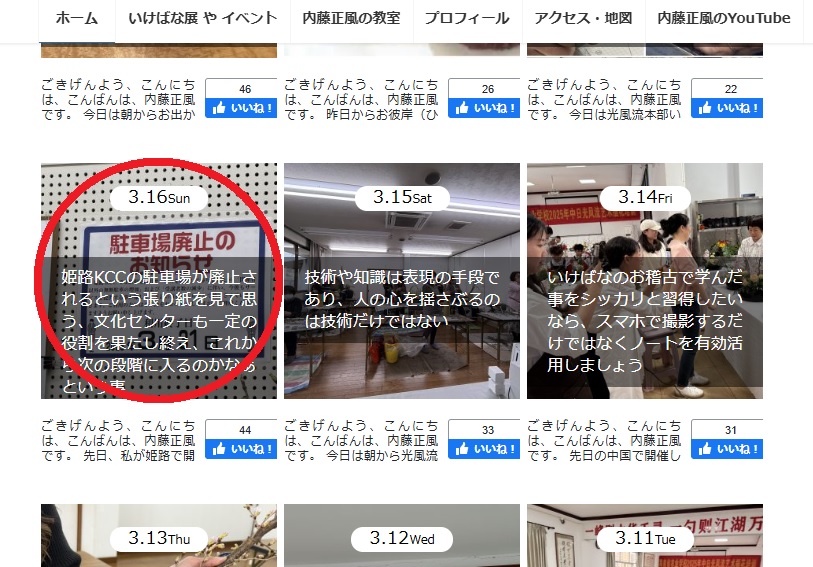正にこれから、いけばなの魅力が再認識され、いけばなの価値が高まってゆく時代になると思います
ごきげんよう、こんにちは、そしてこんばんは、内藤正風です。
一週間ほど前に「姫路KCCの駐車場が廃止されるという張り紙を見て思う、文化センターも一定の役割を果たし終え、これから次の段階に入るのかなぁという事」というブログを書きました。
このブログを昨日なにげなく読みかえしながら、”文化センター” や ”地域の婦人会” や ”公民館活動” と呼ばれるものがこれまでに果たしてきた「地域で身近に手軽に文化に触れることが出来る」という役割、すなわち言い方を変えれば「すそ野を広げる」という取り組みによって生み出されたものと、これからの時代の中での文化、特にいけばなを中心に見た中での人々と文化の関わりというようなことについて、色々と思ったので、今日はそんな事についてブログを書きたいと思います。
”いけばな” の大衆化には、女学校や婦人会活動が大きな力を発揮しました
いけばなは戦後からバブルのころまで、女性の花嫁修業の一つと位置付けられ、大いに華やかなりし時代でした。この時代は結婚前には、いけばなやお茶のお稽古に行くという考え方がスタンダードであり、嫁入り道具の中にいけばなの師範のお免状が無いと格好が悪いと思われていました。
これは明治大正時代の子女教育の流れを受け、日本各地に女学校がたくさん設立されたことや、戦後における地域の婦人会活動が活発になり、そういう中で女学校の中に正科目やクラブ活動としていけばなが行なわれるようになったり、婦人会活動の中でいけばなが行なわれるようになったのが、その土台になっていると言う事ができると思います。
そしてその事によって ”いけばな” のすそ野は大きく広がりました。万人というか、ほぼ大半の女性が ”いけばな” を嗜むという、これまでの日本には無かった状況を生み出すことが出来、正にいけばなを大衆化することに成功したのです。
戦後の日本は、「憧れ」を手に入れてゆく時代でした
そしてこのようにして皆が「いけばなを行ないたい」と思い、実現することが出来るようになったのは、日本が戦後高度成長時代の中で ”豊かになった” という事が一番大きな原因だと思います。
戦前までの日本人は大半が貧しかったです。食べるものの心配をして日々生きてゆかなければならない人がその大半を占めていました。しかし戦後の高度成長時代になって、みんなが豊かになり、それまで思っていた憧れを一つずつ手に入れていったのです。
お金持ちの家にしかなかったテレビを買うことができるようになった。お金持ちの家に設えられていた床や床の間を家を建てたり買ったりして自分も手に入れることができた。お金持ちの子女しか行くことができていなかった高等教育を自分の子供にも受けさせてやることができるようになった。これらすべて、憧れを手にいれる事ができたという事なのです。
そしてこういう中の1つに、いけばなも入っていたのです。
大衆化は陳腐化につながる
このように時代背景や世の中のニーズにぴったりと当てはまった ”いけばな” は、これまでのいけばなの歴史上にない隆盛を極めました。とはいえその隆盛はバブル崩壊の頃には、お稽古をされる方の減少と共にその面影をなくし、今では ”いけばな冬の時代” と表現されるようになってきています。
ちなみに私は、 ”いけばな” が現在のような状況を迎えた要因の中の大きな一つに、大衆化したことがあると思っています。これは全ての事柄が同じことを言えると思うのですが、大衆化するという事は一過性のブームであり、ブームはいつか終焉を迎えるのが其の常ですので、大衆化した時点でそのものは陳腐化してしまい、世の人々にとって特別な魅力も価値もなくなってしまったという事なのです。
これから「いけばなの価値」が認められる時代になる
バブル崩壊から30年以上が経ち、いけばなを学ばれる方が、今、どうなっているかというと、いけばなをお稽古される中心は若い女性という感覚は無くなり、どちらかというと、ひと年を重ねた大人な人たちがお稽古をされるようになっていますし、男性もいけばなのお稽古をなさるようになってきて、以前とは全く違う状況になっています。
そして私はこの状況を見ながら、とりあえずは良い傾向にむかっていると思っています。その理由はハッキリしています。結婚するときに免状が無いと格好が悪いというような人ではなく、いけばなに興味を持った方がお稽古をして下さるようになっており、本来あるべき姿に戻っていると言えますと共に、大衆化とは逆の方向に歩みが進んでいると感じるからです。
つまり、大衆化によって陳腐化してしまったいけばなが、大衆化とは逆の方向に進む事によって、いけばなを嗜んでいるという事から価値を感じて頂くことが出来るようになっているているという事です。
なので私は、これからがいけばなの価値を再認識してもらうことができる時代になってゆくと思っているという事なのです。
内藤正風PROFILE

-
平成5年(1993年)、光風流二世家元を継承。
お花を生けるという事は、幸せを生み出すという事。あなたの生活に幸せな物語を生み出すお手伝いをする、これが「いけばな」です。
光風流の伝承を大切にしながら日々移り変わる環境や価値観に合わせ、生活の中のチョットした空間に手軽に飾る事が出来る「小品花」や、「いけばな」を誰でもが気軽に楽しむ事が出来る機会として、最近ではFacebookにおいて「トイレのお花仲間」というアルバムを立ち上げ、情報発信をしています。ここには未経験の皆さんを中心に多くの方が参加され、それぞれ思い思いに一輪一枝を挿し気軽にお花を楽しまれて大きな盛り上がりをみせており、多くの方から注目を浴びています。
いけばな指導や展覧会の開催だけにとどまらず、結婚式やパーティー会場のお花、コンサートなどの舞台装飾、他分野とのコラボレーション、外国の方へのいけばなの普及、講演など、多方面にわたり活動し多くの人に喜ばれています。